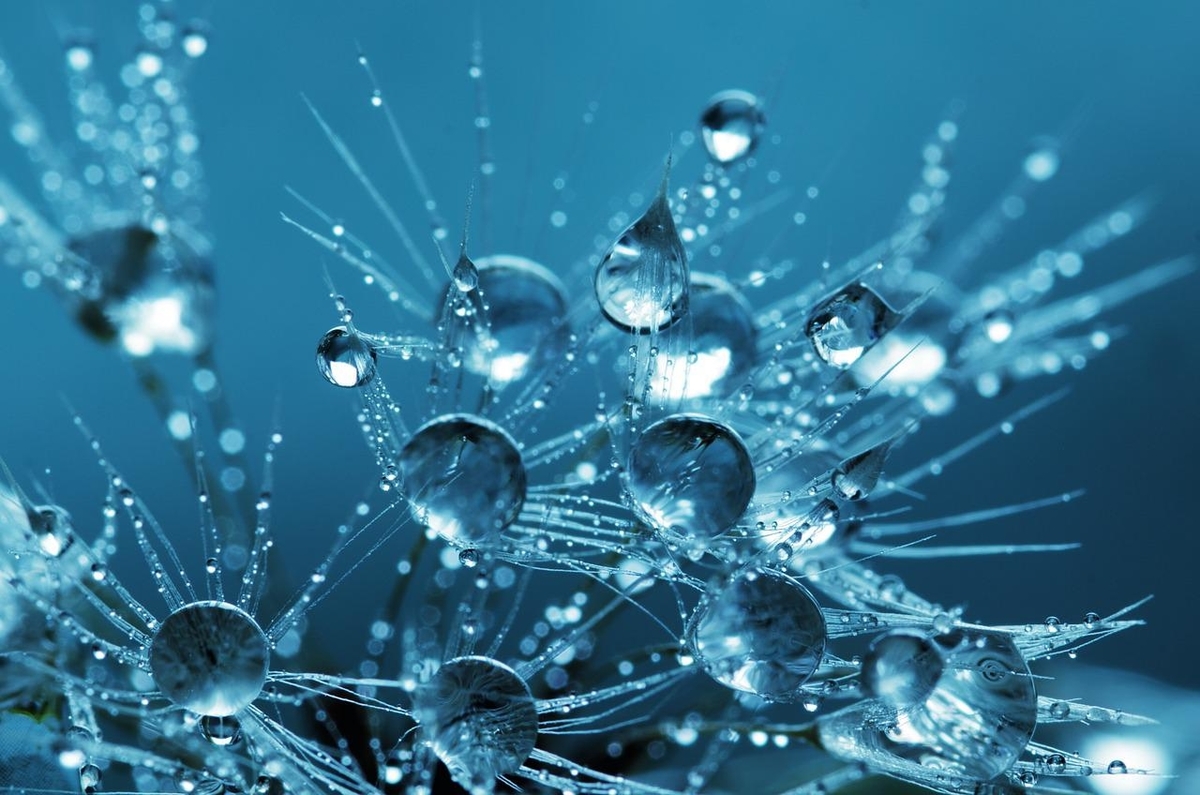訓読 >>>
519
雨障(あまつつ)み常(つね)する君はひさかたの昨夜(きぞ)の夜(よ)の雨に懲(こ)りにけむかも
520
ひさかたの雨も降らぬか雨障(あまつつ)み君にたぐひてこの日暮らさむ
要旨 >>>
〈519〉雨を口実にいつも家に籠っておられるあなたは、夕べ来られた時に降った雨に、すっかり凝りてしまわれたのでしょうか。
〈520〉雨が降ってこないものか、それを口実に、あなたに寄り添って今日一日暮らそうものを。
鑑賞 >>>
519は大伴女郎(おおとものいらつめ)の歌、520は後にある人が追和した歌。大伴女郎は、大伴安麿(おおとものやすまろ)と石川郎女(いしかわのいらつめ)の娘で、最初、今城王(いまきのおほきみ)の父に嫁いで今城王を生みましたが、夫と死別したのか、その後、異母兄妹の大伴旅人の妻となりました。家持の実母であり、筑紫で他界し、旅人が亡妻挽歌を詠んだのがこの女性ではないかとされます。520は「後の人の追同(おひなぞら)ふる歌」とあり、作者は不明ながら、編者の家持が、母である女郎の歌に目をとめて詠んだものではないかとする見方もあります。
「雨障み」は、雨に妨げられて家に籠る意。この時代、雨は天から降り注ぐ畏ろしい霊気を帯びたものとされていましたから、恋人に逢いたくとも、雨に濡れて出かけることは忌避されました。519では、昨夜の雨に濡れた男が、今夜はもうやって来ないかもしれないという不安にかられながらも、いたわりの気持ちが感じられる歌になっています。窪田空穂は、「おおらかで、優しさがあり、その階級を思わせる人柄である」と述べています。「ひさかたの」は、悠久の天の彼方の意で「雨」の枕詞。
520の「雨も降らぬか」は、降らないのか、降ってくれよの意。「たぐひて」は、寄り添って。上の歌の女郎の心を思いやり、女郎に代わって詠んだ形のものですが、窪田空穂は、「上の歌のつつましやかな、人柄なのに較べると、この歌はただ媚態を示しているだけのものである」と評し、また「女郎がもしこの歌を見たならば、斥けたであろうと思われる」と述べています。